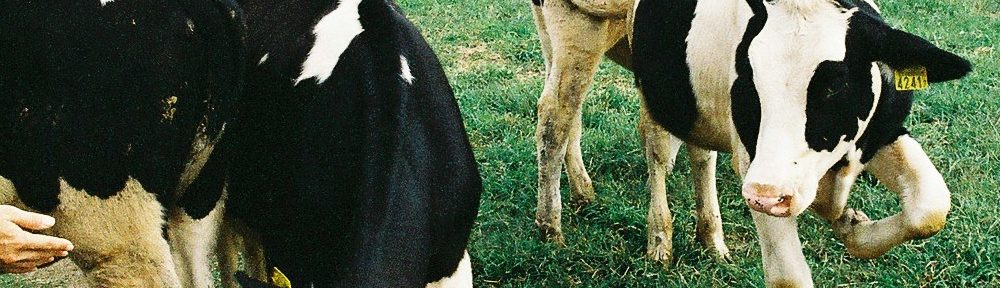老後の楽しみに、と現在一生懸命ジャズ・ギターの練習をしている。
と言っても、まだ入り口の入り口の入り口。目標はセッション・デビューなんだけど。なんかお金払ってジャズのアドリブをそれぞれが順番で取るようなセッションがあるらしいのだが、そこで度胸試しが出来るようになるまで、が当面の目標かな。
なんで20年も放っておいたギターをまた再開する気になったかというと、DTM(Desk Top Music)がきっかけ。それだけ聞くとなぜ?という話だが、去年だかに急にDTMやる気になって、まあ、イチからちゃんとやろう、と、いきなりオリジナル曲、などという無謀なことはせず、まず既存の曲をコピーし、ソフトの使い方の習熟、またアレンジ、ミックスの勉強をしようと何曲かカバー曲を作ったわけ。
で、作る度にアレンジ、ミックスの精度も上がり、これは良いな、では次に取り組むこの曲のカバーがちゃんとできたら、オリジナル曲も取り掛かろうかな、と思った曲が、それほど目立たなくはあるが、カッティングのギターがばっちり入ってる曲で。このカッティングギターばかりはいくらDTMの音源が進化したと言えど、簡単にはPC上では再現出来なかった。
ま、それならギターはあるのだし、自分で弾けばいいかな、と思ったが、何しろギターのハイポジションのコードが分からない(笑) 6弦、5弦のルート音がなんとなく分かる程度で、指板の音程など全く知らない。・・・あれ?俺、こんなレベルでギター投げ出したんだっけ?とちょっと愕然とした。
長年、ギター持ってるのに、例えばギターの指板のことだけをとってもどこが何の音かとか全く把握できてなくて、なんとなくギターに対して申し訳ない気持ちがあったので、ここで一念発起、ギターの指板を全部覚えよう! これを機にちっとはギター弾けるようになろう!と決意したわけ。
だが、ギターの指板を把握するつもりでギター練習すると、それはそれで非常に時間がかかり、そんなことで現在DTMは予想通り、活動停止している。(どっかのタイミングで再開したいけど。)
で、行きついた先がジャズギター。ちなみにジャズの知識ほぼゼロ(^^)
そんな私がなぜジャズギターか?というと、指板の音階、そしてルートに対する度数をきちんと把握しながら、練習するには何がいいんだろう?とネットの記事やYouTubeを漁っていたら、ジャズ初心者の練習で、ひたすら曲のコードトーンをなぞる、という練習があって。ジャズなので基本4和音。ルート、3rd、5th、7thの4つの音をひたすら見つけてそれを弾くのだが、これがなかなか・・・
主要なコードだけでもルートCなら、CM7、C7、Cm7、Cm7♭5、Cdim7とこれぐらいあり、これをもちろんCルートだけではなく、いろんなルート音で弾けるようにならなければならない。それも毎回ルートから弾くのでは音楽にならないので、3rdから弾く、5thから、7thから・・・とまあ、これがかなり大変なんだわな。
多分、10代、20代の頃の私であれば速攻止めてるが、そこは半世紀近く生きた男の大人力(笑) 我慢することの先に喜びがあることを知っている今の自分なら我慢して練習することが出来る。いやあ、歳取るのも悪いことばかりじゃない。(基本悪いことの方が多いが)
ということで話長くなったが、今はとにかく色んなジャズスタンダードのコード進行を見つけては、チロチロとひたすらコードトーンを追う練習をする毎日。コードトーンしか弾かないのだからコード感はあるが、やたらと素人くさい演奏。いや、演奏とも言えない。誰に聞かせてもいかにも練習曲らしい練習曲を練習してるとしか聞こえないだろう。それでも、譜面に書かれた模範となる音符以外に指板上に音を見つけ、ちょっとでも脱線出来たらうれしい。
これこそアドリブの第一歩である。ルートに対して何度の音を弾いてるか分かるから、現在地が把握できているし、次に進む場所もわかる。非常に小さな一歩だが、私にとっては大きな一歩。なにせこれまでは、譜面に書いてある音以外にはみ出すことなど全く出来なかったのだから。
まだ書くことあるな(笑) このひたすらコードトーンを追う練習は、アドリブの基礎固めとして非常に有用であるのは日々実感しているのだが、また、ジャズスタンダードのコード進行がいい。ブルースや一部のフォークのように単純すぎず、かと言って一部のポップスのようにひねくれ過ぎてもいない。
ジャズというと、やたらとコードにテンションが乗りまくって、コード進行も音楽の中でも一番難解、と思われがちだが、基本のコード進行はそうでもない。その気になれば、色々テンションもくっつけれるというだけで、基本的には、2-5-1の繰り返し、曲内で部分転調と言える箇所もあるが、大体4度上に移調するのが多く、弾いてみれば分かるが、それほど転調感もない。(もちろん例外あるよ、ジャイアント・ステップとかああいうの)
そんな訳で、単調過ぎず、かといって難しすぎずで、練習するにはちょうどいいコード進行の曲がいっぱいある。
だから、ジャズスタンダードをひたすらコードトーンで追う練習というのは、なにもジャズギタリストを目指す人だけじゃなく、ブルース、ロック、フュージョン・・・全てのギタリストにとってとても有用な練習だと思う。コードトーンが完璧なら、スケールはこのコードトーンを足掛かりに何音か足すだけだから、いきなりスケール練習するよりはるかに理解が早い。
例えばリディアン・スケールを練習するとして、実際に1曲丸々リディアンで構成されてる曲なんてそうない訳で、そうすると現実にありもしないリディアンばかりの繰り返しを練習しても、リディアンスケールはそれで覚えれても、実際の曲中でのリディアンの使いどころが分からないままだと思うんだよね。
それよりはともかくコードトーンを覚えて、そこから、ここはリディアン、ここはドリアン、ここはロクリアンなどと派生させて一気に覚えていった方が、実際の音楽にそった形でそれぞれのスケールが覚えられると思う。
・・・ここまで読み切った人がいたら教えてくださいね(笑) なんかえらそうに書いたが、どこのポジションから、どの音程からでもコードトーンを繰り出せるようになるにはまだまだ時間が掛かりそう。もちろん、スケールを元にしたフレーズのストックも全然これから。先はまだ長いが、楽しみながら続けたいと思う。
きょうはなんとなく口語調で書いてみたが、なんか70年代、80年代のライナーノーツみたいなノリになるな。